空気中を舞う猫の抜け毛を、鼻や口から吸い込むと、私たちの肺に悪影響がないか、心配になりませんか?
- 人が猫の毛を吸い込んだとき、問題ある?
- 気を付けなくてはいけない症状
- できるだけ猫の毛を吸い込まないための予防方法
猫の毛を鼻や口から吸い込むことで肺の中に溜まり、吸い込んだ毛が絡み合わないか、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、猫の毛を鼻や口から吸い込んでも、肺など人体にはほとんど影響がありません。
しかし、猫が大量の抜け毛を体内に取り込むと、毛球症など怖い病気の発症リスクがあり、危険です!
猫も飼い主さんも、健康で快適な生活を送るため、正しい対応を行うことが大切です。
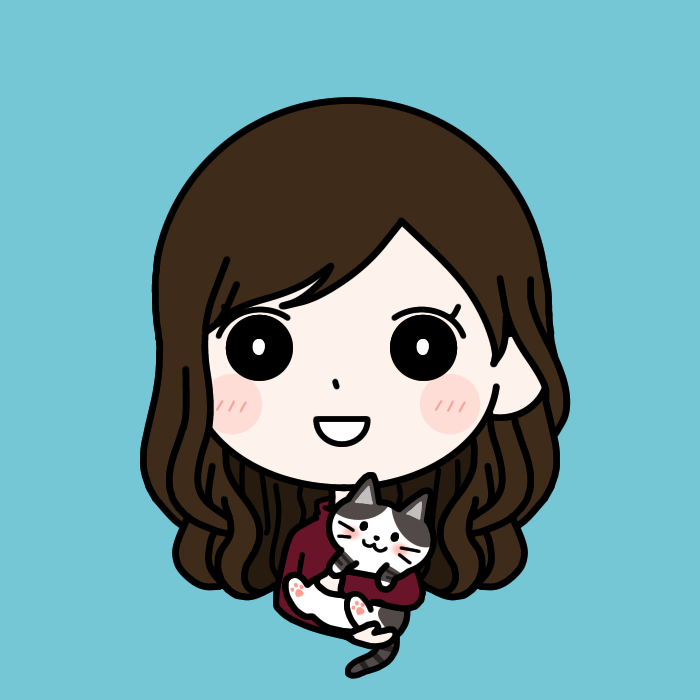
猫の専門資格をもつわたしが、【人が猫の毛を鼻や口から吸い込むことで、肺などに危険があるか】について、分かりやすく解説しています。
猫の毛の処理については、こちらの記事で解説しています‼↓↓
【猫】布団と毛布が毛だらけ…簡単に取る方法は?おすすめの対策グッズはゴム手袋!
猫の毛を吸い込んでも、人にほとんど害はない

猫のことをインターネットで調べると、下記のような怖い内容を目にしたことのある飼い主さんは多いのではないでしょうか。
- 猫が毛づくろいをすると、舐めとった毛が猫の体内で「毛球症」になることがある
- 猫の毛を常に清潔にしないと、ダニやノミなど寄生虫がつきやすい
- 猫の毛に付いた寄生虫は、人体へ感染するものがある
【猫吸い】と言われる、猫の体に顔をうずめて直接猫のニオイを吸うことで鼻から表面の抜け毛が入り込み、人の肺へ侵入していると思われがちです。
しかし、【猫吸い】で鼻から猫の毛を吸い込む、この仮説は半分間違っています。
物理的に、鼻から猫の毛が入ることはほとんどないです。
口からの侵入は、人が呼吸するたび、空気中に蔓延している猫の毛を少量ずつ体内に取り込んでいます。
しかし、喉を通過して胃の中で処理されるため、猫のように「毛球症」にはならないのです。
結果、人の体内に猫の毛が吸い込まれても、無症状で問題ありません。
ここで注意したいのは、猫の毛にあるアレルゲンによって、アレルギー反応が起こる人もいる点を覚えておきましょう。
猫の毛を吸い込んでも人に害がない理由2つ

猫の毛を吸い込んでも人に害がない理由は、以下の2つです。
- 鼻から吸い込んだとき
- 口から吸い込んだとき
順番に解説します。
鼻から吸い込んだとき
猫の毛を鼻から吸い込んでも、人体に害はありません。
鼻の中には、外からの異物が入らないように鼻毛が生えていて、物理的に難しいためです。
鼻毛は外からの異物を感知すると、くしゃみで体外へ出す構造になっています。
しかし、取り込まれた毛に細菌や寄生虫が寄生していると肺まで届いてしまうこともあるため、注意が必要です。
口から吸い込んだとき
猫の毛を口から吸い込んでも、人体に害はありません。
口から飲み込んだ毛が喉に触れると、異物の侵入を感知し、咳をしながら体外へ排除する働きをするためです。
口から入った猫の毛は、しばらく喉に違和感ががあっても、留まることがありません。
これは喉に直接毛が当たっているのではなく、神経過敏になっているだけで、実際にはすでに通過しています。
さらに、喉を通過した猫の毛は呼吸器官ではなく、消化器官の流れで移動するため、肺へは届きません。
同じように口から入ってきた水や食べたものと一緒に胃の中まで運ばれ、強い胃酸によって処理されます。

人の胃は、猫の胃と比べると数十倍の大きさがあるため、全く問題ありません。
できるだけ猫の毛を吸い込まない方が良い理由2つ

できるだけ猫の毛を吸い込まない方が良い理由は、以下の2つです。
- 猫の毛を吸い込んで症状が出る人は「猫アレルギー」
- 肺がんのリスクもある
順番に解説します。
猫の毛を吸い込んで症状が出る人は「猫アレルギー」
猫の毛についているアレルゲンに反応し、喘息や気管支炎の症状がでることがあります。
このアレルゲンによって出る症状を総称して【猫アレルギー】と呼びます。
| 部位 | 主な症状 |
| 皮膚※ | 赤み・かゆみ・腫れ・痛み・じんましん など |
| 目 | かゆみ・流血・腫れ など |
| 鼻 | くしゃみ・鼻水・鼻づまり など |
| 喉 | かゆみ・痛み・咳・息苦しい |
猫アレルギーの症状を起こすアレルゲンの代表的な物質は、たんぱく質「Fel d1」(フェル ディ ワン)です。
通常は猫の唾液や皮脂腺に含まれていますが、乾燥すると空気中を浮遊します。
人の体中にある免疫が、吸い込んだ「Fel d1」(フェル ディ ワン)を異物と認識し、体外へ排除する働きがアレルギー反応を引き起こしています。
人によって症状が違いますが、皮膚症状と合わせて呼吸器症状が出た場合はアナフラキシーと言われ、危険です。

約20%の人が、”猫アレルギー”と言われています!
肺がんのリスクもある
猫の毛を吸い込むことで、肺がんのリスクがあります。
肺まで猫の毛が入るのではなく、毛についたフケやダニ・ノミなどの寄生虫やハウスダストが原因です。
猫の毛についたフケ、ダニ・ノミなどの寄生虫やハウスダストが人の肺に入り込むことで、肺がん発症のリスクがあると報告されています。
たとえば、アメリカの大学による調査で、猫を飼っている女性は飼っていない女性と比べて、肺がん発症率が2.85倍も高い結果がでているのです。(引用:ペットと肺がん死亡率に意外な関連)
猫の毛を吸い込まないための予防方法3つ

猫の毛を吸い込まないための予防方法は、以下の3つです。
- 毎日ブラッシングする
- 被毛をきれいにする(お風呂)
- 掃除をマメにする(コロコロをかける)
順番に解説します。
毎日ブラッシングする
猫の毛を吸い込まないためにも、毎日のブラッシングを日課にしましょう。
ブラッシングは、猫が毛づくろいをするときに舐めて口に入る毛を減らす役目があるためです。
また、猫の「毛球症」や消化器系の病気の予防にもつながります。
毎日のブラッシングは愛猫の毛並みを整えてたり、毛の健康チェックを行ったりなど、大事なことです。
猫の体についた抜け毛を空気中に舞う前に取り除いてあげると、吸い込む量を減らすことができます。
▶猫毛づくろいが下手な理由3つ!ボサボサ/べちゃべちゃ/毛割れを上手にケア!
被毛をきれいにする(お風呂)
毛づくろいで舐めた毛を、お風呂できれいにしてあげましょう。
「猫は毛づくろいをすることで被毛を清潔に保てるため、お風呂は必要ないのでは?」と思われた方もいるのではないでしょうか。
これは完全室内飼いになったことで人と触れ合い、毛に付いた猫の唾液が人に「猫アレルギー」を発症させる可能性があるためです。
お風呂が嫌いな我が家の猫には、シャンプータオルを使ってきれいにしています。
お手頃価格のため、長期的に使いやすくてお気に入りです。(*’▽’*)♪
掃除をマメにする(コロコロをかける)
こまめに掃除をすることで、室内に舞う毛を取り除き、吸いこまない環境を保つことが大切です。
猫の毛は、床・壁・天井・カーテン・家具・家電など室内のあらゆる場所についています。
人の服にも付着するため、猫の毛がついた服は室内に持ち込まないのが理想です。
【これはおすすめしません!】猫の毛を刈ってしまう
猫の抜け毛はいたるところに落ち、換毛期では抜け毛の量が10倍になるため、丸刈りする人がいます。
しかし、おすすめしません。
というより、絶対にやめてください。
猫は自分の体温を調節できない動物で、外気との温度調節を被毛で行うためです。(人でいう、外気の温度に合わせて着る服を変えている感じ)
夏は毛の中の通気性が良くなるように、冬は体の熱が外へ逃げないように、自分の毛を使って体温調整しています。
また、本来の機能が丸刈りすることで衰えていき、抵抗力の低下につながるため、避けましょう。
見た目も品祖になります。
まとめ:猫の毛を吸い込んでも問題ないけど、症状には個人差があるよ!
今回は、猫の毛を人の鼻や口から吸い込んだら、肺に対する影響について、解説しました。
人は、猫の毛を吸い込んだとしても肺に入ることが少なく、口から入り込んだとしても喉を通過し最終的に胃の中で処理されるため、問題ありません。
しかし、毛に付着した猫の唾液やおしっこによってアレルギー反応を起こす、「猫アレルギー」症状が出る人は注意が必要です。
猫を飼っている女性は、猫の毛に付着したフケ、寄生虫などが人の肺に入り込み、肺がんになるリスクが2.85倍も高い報告が発表されています。
目に見える【猫の毛】だけではなく、毛に付着したフケ・寄生虫・唾液・おしっこを吸い込まないよう、予防していきましょう。
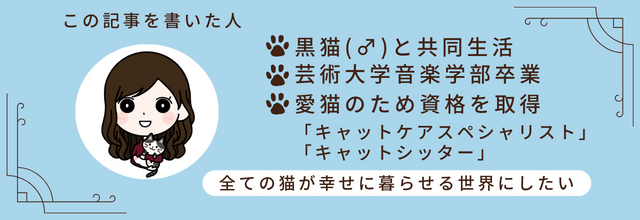

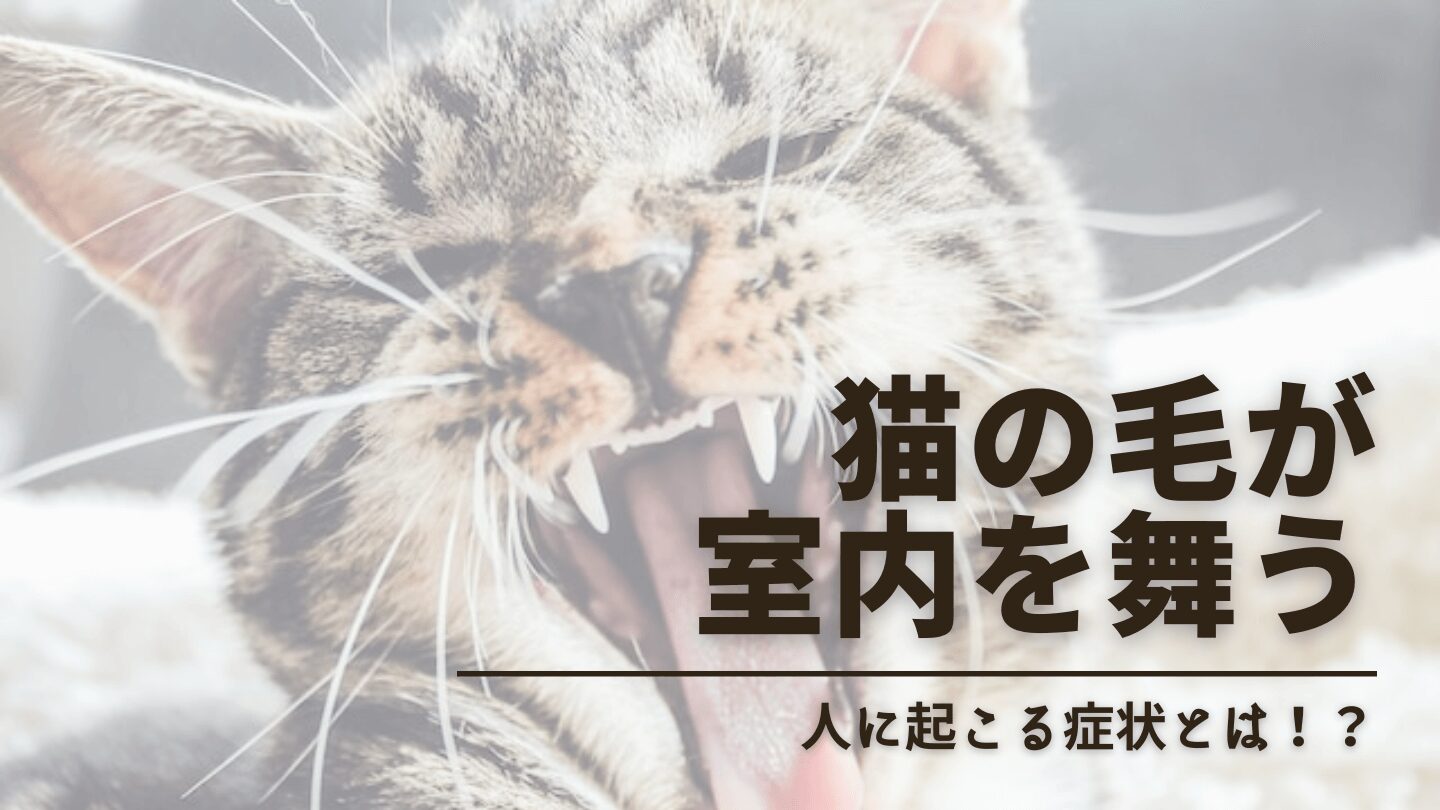

コメント