
我が家の愛猫は、飼い主である私の髪の毛を毛づくろいするのに、引っ張ったり舐めたりして困ってます。
なぜ猫は飼い主の髪の毛を毛づくろいするのかな?
今回は、”猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐めるのはなぜ”について、紹介します。
- 猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐める理由
- 猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐めるときの注意と対策
- 猫に髪の毛の毛づくろいを止めさせる方法
結論からお伝えすると、猫が飼い主の髪を毛づくろいするような”引っ張る/舐める”仕草をするのは、信頼している証です。
髪の毛を毛づくろいしながら、引っ張ったり舐めたりすることで、自分のにおいをつけています。
愛猫がすりすり寄って髪の毛を引っ張ったり舐められたりされると、『じゃれてるのかな?』と思われるかもしれません。
しかし、猫なりの立派な”愛情表現”だとしても、危険なことがあれば、やめさせる必要があります。
そこで、猫の専門資格をもつ私が、”猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐める理由”について、分かりやすく解説します。
猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐める理由3つ

猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐める理由は、以下の3つになります。
- 猫から信頼された証”愛情表現”だから
- 飼い主のニオイを感じやすいから
- 動く髪の毛がおもちゃと勘違いしている
3つの理由について、解説します。
①猫から信頼された証拠”愛情表現”だから
猫が飼い主さんの髪の毛を毛づくろいするのは、信頼している相手に対しての、愛情表現です。
猫同士で毛づくろいしあう”アログルーミング”と呼ばれる行動で、お互いの『自分では毛づくろいできない顔周りや背中の部分』を助け合う意味があります。
まだ自分で毛づくろいできない子猫をお母さん猫が毛づくろいしてあげたり、兄弟で毛づくろいし合ったりするのは、相手を信頼している証拠です。
この気持ちは、大好きな飼い主さんへも同じように向けられます。
愛猫が髪の毛にすりすり寄ってきて、毛づくろいをするように髪の毛を噛む/舐める/引っ張るなどの行動をしたら、『大好きだよ』と伝えに来たのかもしれません。

ちなみに、自分で毛づくろいするのは、”セルフグルーミング”といいます。
②飼い主のニオイを感じやすいから
猫にとって、大好きな飼い主さんのニオイ=”落ち着けるニオイ”のため、髪の毛を毛づくろいで引っ張ったり舐めたりすることがあります。
髪の毛を毛づくろいする理由は、人の頭皮には無数の毛根があり、飼い主であるあなたのニオイを感じやすいためです。
飼い主である、【あなたのニオイを感じやすい場所】という理由から、頭を選んだということになります。
猫は臭覚が優れていて、ニオイによって分析・判断できるため、飼い主かどうかの判断もニオイで嗅ぎ分けることができるのです。

猫は大好きな飼い主さんのニオイを嗅いで、リラックスします。
また、髪の毛を毛づくろいで舐めることで、自分のニオイと合わせる意味もあります。
③動く髪の毛がおもちゃと勘違いしている
髪の毛が動くことで、”おもちゃと勘違い”してじゃれるため、髪の毛を毛づくろいのように見える場合があります。
この現象は、動いているものへ敏感に反応する野生の習性が残っているためです。
猫の視力は人に当てはめると0.1ほどしかないですが、視力を補うため、動体視力が優れています。
また、聴覚も鋭く、獲物が動くときの風の流れや音・音までの距離を正確に分析できる能力も備わっています。

猫じゃらしやおもちゃは、動くものへの習性を上手に使った遊びです。
ちなみに、聴覚については、こちらの記事でも解説しています‼↓↓
猫の目の上の毛が薄いのはなぜ?2つの理由や”はげる病気”の危険性もあり注意‼
猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐めるときの注意点と対策3つ

猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐めるときに注意点と対策は、以下の3つになります。
- 髪の毛の誤飲をなるべく未然に防ぐ
- 抜けた髪の毛はこまめに掃除する
- 整髪料/アクセサリーがついた状態では絶対にだめ!
3つの注意点と対策について、解説します。
①髪の毛の誤飲をなるべく未然に防ぐ
髪の毛を毛づくろいすると誤って食べてしまう可能性があるため、猫の愛情表現でも長時間の毛づくろいはやめさせましょう。
人の髪の毛は猫の被毛と同じで食べても消化されないため、少量であれば吐き戻したり、うんちと一緒に排泄されたりします。
しかし、大量に飲み込んでしまうと、胃や腸に”毛球症”と似た状態ができるため非常に危険です。

我が家の猫もたまに、うんちと一緒に私の髪の毛が出てきます。
誤飲を防ぐには、飼い主さんの頭皮のニオイを抑えると、改善が期待されます。
- 汗をかいた状態で猫に接しない
- 髪の毛と頭皮を洗い、清潔な状態にする
万が一苦しそうにしたり、下記のような異変を感じたら即、動物病院を受診してください。
嘔吐 / 下痢 / 食欲不振 / 便秘
②抜けた髪の毛はこまめに掃除する
部屋をこまめに掃除することで、室内に髪の毛が落ちていない状態にしましょう。
猫は髪の毛の毛づくろいだけでなく、床に落ちてる髪の毛を誤って誤飲する可能性があります。
特に、長い髪の毛は誤飲すると胃や腸で絡みやすいため、猫と接するときはゴムでしばる・まとめ髪にすることが望ましいです。
③整髪料/アクセサリーがついた状態では絶対にだめ!
整髪料やピアスなどのアクセサリーを身につけた状態で、猫と触れ合うのはやめましょう。
整髪料は猫にとって有害物質ですし、ピアスなどのアクセサリーは誤飲する可能性があります。
猫は毛づくろいに夢中だと誤って口に入れてしまうことが考えられるため、”猫と一緒にいるときは、整髪料やアクセサリーをつけない“ことが大切です。
猫が飼い主の髪を毛づくろいを止めさせる方法3つ

猫が飼い主の髪を毛づくろいを止めさせる方法は、”他に興味を反らす”ことです。
猫が飼い主の髪を毛づくろいを止めさせる方法として、以下の3つを選びました。
- 動きのあるおもちゃを使う
- 部屋の中を移動してみる
- 柑橘系のシャンプーを使う
3つの方法について、解説します。
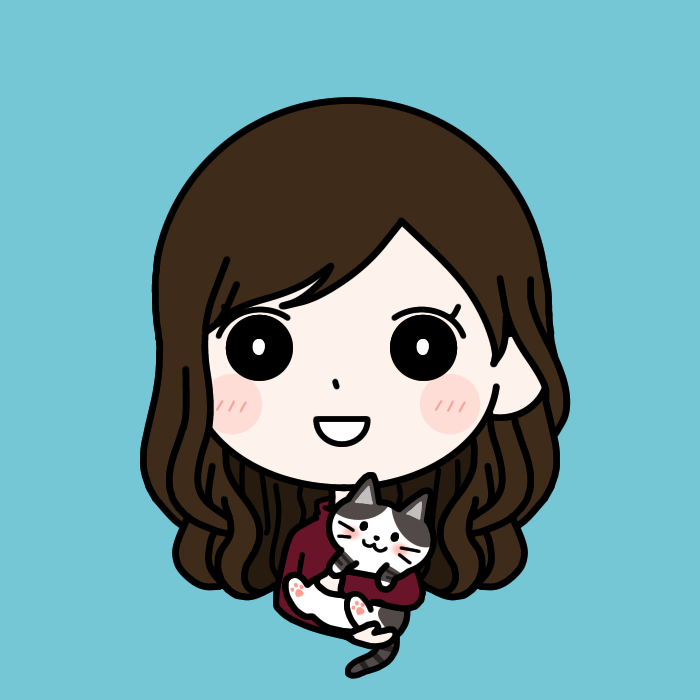
この記事では、実際に私が使っている方法を紹介していきます。
猫の性格によって使える方法が違うため、いろいろ試してくださいね。
①動きのあるおもちゃを使う
猫の動くものへ反応する習性を利用し、動くおもちゃに興味を移させることで、毛づくろいをやめさせる方法です。
我が家の猫は、中に鈴が入ったボールを遠くへ投げると追いかけていき、そのままボールで遊び始めます。

しばらくは、部屋中鈴の音が鳴りっぱなしです。
音が気になる方は、鈴の入っていないボールでも同じような効果があります。
遊び始めは、勢いよくボールが飛んでくることがあるため、飼い主さんもケガしないように注意してください。
\猫は毛玉ボール好き/
\安全面もGOOD‼/
②部屋の中を移動してみる
猫が髪の毛を毛づくろいし始めたら、飼い主さんが部屋の中を移動して、毛づくろいをやめさせる方法です。
急に立ち上がった飼い主さんに対して猫は、『え、どこいくの?』と興味がそれて、飼い主さんの後をついてくる可能性を狙います。
この原理はおもちゃの時と似ていて、おもちゃのかわりに飼い主さんが動くことで、興味が髪の毛から反らすのです。

絶対にやってはいけないのが、【おやつをあげること】。
一度おやつをあげてしまうと、猫はおやつをもらえる方法として記憶します。
他にもありますが、【猫が普段興味を示すもの】を与えることで、興味を反らす方法です。
- 愛猫お気に入りのおもちゃ
- 愛猫お気に入りの毛布・タオル
- 大好きな飼い主さんのニオイがするもの(服・タオルなど)
猫の好きなもので、一度試してみてください。
③柑橘系のシャンプーを使う
柑橘系のシャンプーを使うことで、髪の毛の毛づくろいをやめさせる方法です。
猫は、柑橘系に含まれている「リモネン」成分が苦手なため、髪の毛から柑橘系の香りがすると、近づかなくなります。
この方法は、猫の専門資格を持つ方ならご存じの、ある意味オーソドックスな方法です。
しかし、私はあえて、この方法を使いません。
理由は、『香りの度合いによって、猫が全く寄り付いてくれなくなる』ためです。
まとめ:猫が飼い主の毛づくろいは…愛情表現!でも、危険だからやめさせよう!

今回は、『猫が飼い主の髪を毛づくろい…引っ張る/舐めるのはなぜか?』について、解説しました。
猫が飼い主さんの髪の毛を引っ張る/舐める/噛む理由は、3つありましたが、愛情表現とはいえ危険もあります。
できるだけ、髪の毛や異物を誤飲させないためにも、できるだけ止めさせる対策をとっていきましょう。
猫によって性格も違いますので、安全面に配慮し、いろいろ試してくださいね。
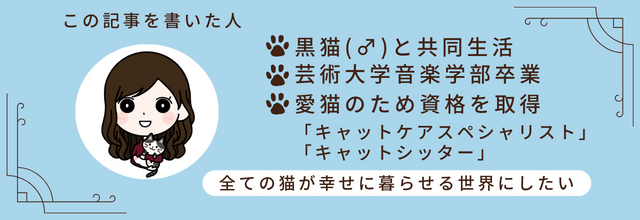

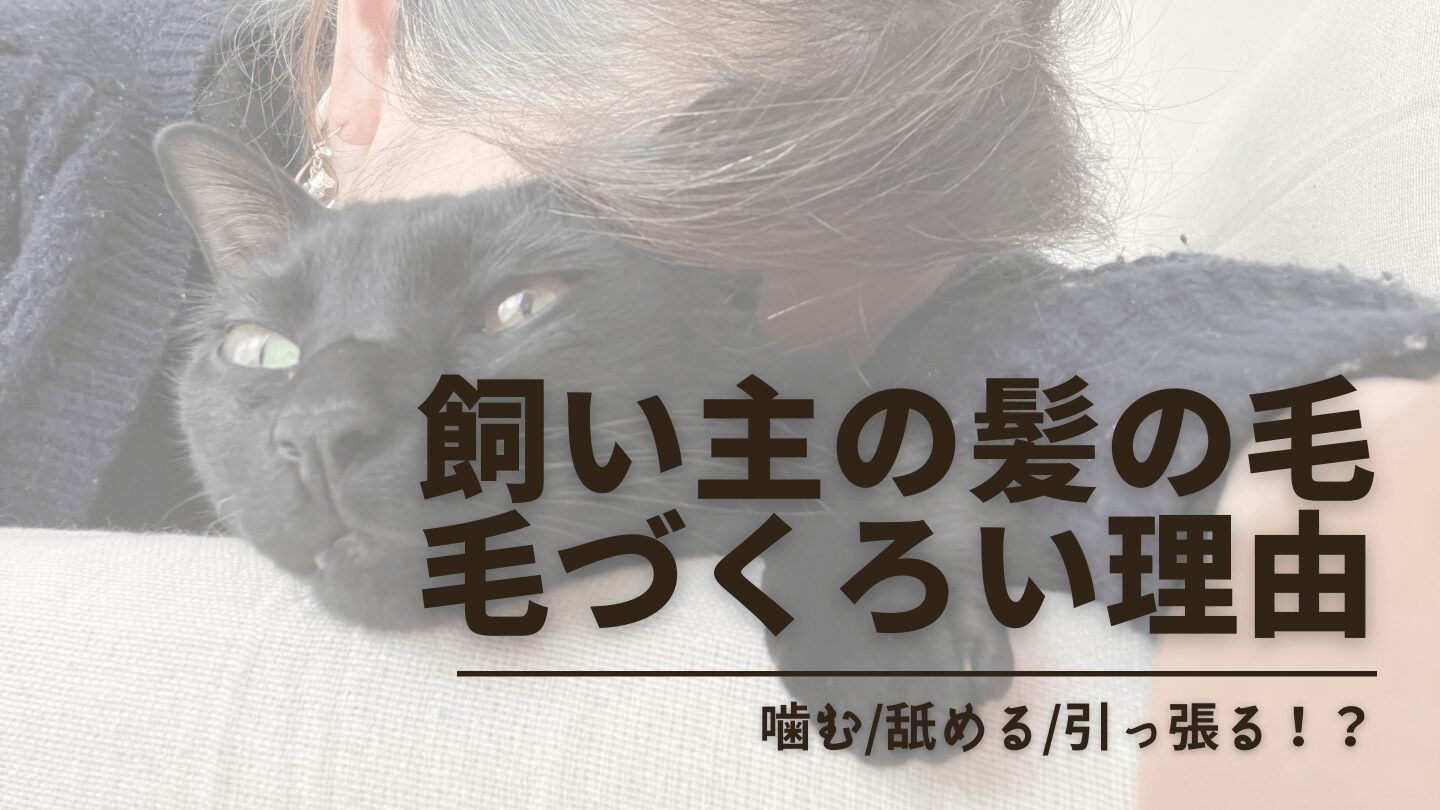

コメント