
猫の毛を撫でるとどんどん毛が抜けてくるんだけど、大丈夫かな?
試しに表面の毛を引っ張っても抜けることがあるから心配。
病気になっていないか、原因が知りたいな。
今回は、こんなお悩みにお答えします。
- 猫の毛を引っ張ると抜ける原因
- 猫の毛を引っ張ると抜ける/撫でると抜ける…考えられる4つの病気
- 猫の毛を引っ張る/撫でると抜けるときの確認ポイント
- 猫の毛を引っ張る/撫でることで抜けにくくする対処法
結論からお話すると、猫の毛を引っ張ると抜ける原因は換毛期だけでなく、皮膚病の可能性があります。
換毛期以外の時期に猫の毛が束になって抜ける場合は、注意が必要です。
しかし、猫の毛が抜けることで考えられる原因がわかれば、正しいケアを行うことができます。
この記事では、猫の専門資格を持つ私が、”猫毛引っ張ると抜ける原因”について解説します。
猫毛引っ張ると抜ける原因5つ!

猫毛引っ張ると抜ける原因は、以下の5つになります。
- ダブルコートの猫種だから(遺伝的要素)
- 換毛期の現象が起きているため
- 過剰なグルーミングで毛が抜けるため
- 外部からの刺激があるため
- 猫が食物・環境アレルギーを持っているため
5つの原因について、分かりやすく解説します。
ダブルコートの猫種のため(遺伝的要素)
猫にはダブルコートとシングルコートの猫種がいます。
ダブルコートはオーバーコートとアンダーコートの2層で、毛の本数が倍になっているため、抜け毛も多いです。
実は、飼い主さんが猫の毛を引っ張ると抜けるのではなく、表面についた抜け毛をつまんで取ってるだけでした!

ダブルコートの代表的な猫種は長毛種だと【ペルシャ】、短毛種だと【アメリカン・ショートヘア】【ロシアンブルー】などになります。
日本の雑種猫は、ほとんどダブルコートです!
ちなみに、特定の猫種は遺伝により、猫の抜けやすい毛質の性質を引き継ぎます。
換毛期の現象が起きているため
換毛期の時期は、毎年3月と11月頃の時期に大量の毛が抜け落ちますが、今回の原因の1つに含めた理由があります。
野生時代には、直射日光の当たる長さで時期が決まっていたため、換毛期の時期は毎年決まっていました。
しかし、完全室内飼いの猫は、直射日光を浴びる時間が少ない傾向にあります。
年中快適な室内で生活する猫は自分の毛で寒さや暑さをしのぐ必要がなくなるため、換毛期の時期が定まらず、年中プチ換毛期のように抜け毛が発生するのです。
したがって、飼い主さんが猫の毛を引っ張ると抜けるのではなく、猫の体の表面についた抜け毛をつまんで取っているだけになります。

イエネコ特有の症状です!
過剰な毛づくろいで毛が抜けるため
過剰な毛づくろいによって、毛が抜け落ちることが考えられます。
原因はいくつかありますが、ストレスや体の不調によることが多いです。
本来毛づくろいをするのは、体を清潔に保つことと緊張した気持ちを落ち着かせるために行います。
同じ場所を長時間毛づくろいするようなら、病気の疑いや危険もあるため、注意して観察しましょう。
ストレスについては、こちらの記事でも解説しています‼↓↓
猫が毛づくろいでブヒブヒ言う…念入りにべちゃべちゃする心理はストレス?4つの理由
外部からの刺激があるため
外部からの刺激を与えることで皮膚にダメージを受け、抜けやすい状態を作っている可能性があります。
皮膚にトラブルがあると、軽く引っ張るだけでも抜けやすいです。
以下のような経験はありませんか?
・毛が絡まってたので、ほぐそうとブラッシングを強めに行った
・首輪をつけたまま過ごしていた
猫は、人以上に刺激が大きく影響するため、注意してくださいね。

ブラッシングで毛を整えるときは、やさしくブラッシングしましょう。
首輪をつける際は、猫が自分で外せない程度で、首まわりに少し余裕があるサイズを選んであげてください。
猫が食物・環境アレルギーを持っているため
猫が特定の食物に対するアレルギーを持っていると、毛が抜け落ちやすくなることがあります。
アレルギー反応のある食物を食べることで皮膚にかゆみや湿疹がでてくると、猫は皮膚や毛を過剰に舐めたり噛んだりします。
過度の毛づくろいは大量の抜け毛を発生させやすくなるため、飼い主さんが猫の表面の毛を引っ張ると抜けたように感じるのでしょう。
愛猫のアレルギーが心配な飼い主さんは、動物病院でアレルギー検査を行ってください。
猫も人と同じように、ハウスダストに対するアレルギーを持つことがあります。
猫の毛が永遠に抜ける…1日に抜ける毛どのくらい?

成猫は約100万本の毛でおおわれているため、部屋のいたるところに猫の毛が落ちていることからも、抜け毛の量が多いと予想されます。
特に、換毛期といわれる年に2回ある時期には、通常の10倍の抜け毛があって大変です。
1日に抜ける本数について正確な統計はありませんが、人の髪の毛は1日に50~100本抜けるといわれるので、猫はその10倍の500~1,000本抜けてる計算になります。

人の髪の毛は、平均10~15万本程度です。
猫の毛を引っ張ると抜ける/撫でると抜ける…考えられる4つの病気とは

猫の毛を引っ張る/撫でると抜ける病気で考えられることは、以下の4つです。
- ノミアレルギー
- 皮膚糸状菌症(ひふしじょうきんしょう)
- 疥癬(かいせん)
- 猫ニキビ
4つの考える病気について、解説します。
ノミ・ダニアレルギー
猫の皮膚や毛にノミ・ダニなどの寄生虫が付着することで、アレルギー症状がでることがあります。
症状は強烈なかゆみがあり、猫は自分の毛や皮膚を過剰になめたり噛んだりすることで、結果的に毛が抜けてしまうのです。
寄生虫が付着していたら、急いでノミ・ダニ駆除と皮膚の治療を行ってください。

動物病院で定期的な予防をおすすめします。
ノアルとモカも、予防してます。
皮膚糸状菌症(ひふしじょうきんしょう)
皮膚糸状菌症(ひふしじょうきんしょう)は、皮膚のやわらかい目・口・耳の顔まわりなどに発症する病気です。
皮膚にカビの一種である糸状菌が付着し、かゆみや発疹がみられます。
糸状菌は人にも感染する【人獣共通感染症】のひとつであるため、飼い主さんも注意してください。

子猫や高齢猫のような免疫の低い猫や、長毛種に多くみられる症状です。
疥癬(かいせん)
疥癬(かいせん)は、ヒゼンダニというダニが猫の皮膚に寄生することで、ひどいかゆみを発症させる病気です。
ほとんどの猫は、耳から顔や頭に感染が広がっていき、顔や耳の根元にかさぶたや脱毛が見られます。
皮膚糸状菌症と同じで、人に感染する【人獣共通感染症】なので、注意が必要です。
猫ニキビ
猫ニキビの初期症状は下あごに黒いポツポツのような汚れができ、放置すると赤く炎症したのち、毛が束になって抜け落ちてしまいます。
猫が違和感を感じると、過剰に下あごをかきむしり、出血する可能性があります。
猫ニキビの初期症状を発見したら、無理にゴシゴシこすらず、ぬるま湯を含ませた清潔なタオルや布で軽くふき取りましょう。
対応に不安を感じた場合は、飼い主さん自身で判断せず、すぐに動物病院を受診してくださいね。
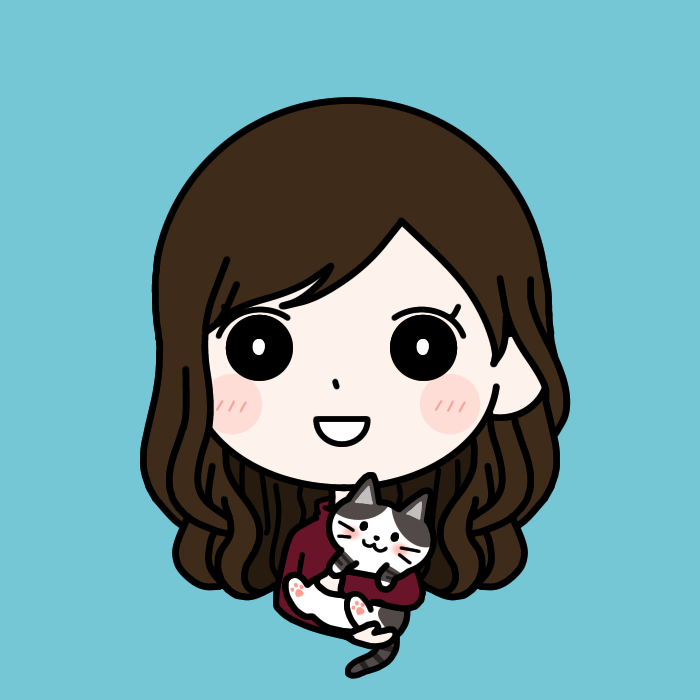
我が家のモカも、下あごに黒いポツポツができたため、動物病院へ連れていきました。
初期段階だったため、処方してもらった専用フォームで、毎日ふき取ってあげてました。
猫の毛を引っ張る/撫でると抜けるときの確認ポイント

猫の毛が抜けるとき確認できる症状は、以下の6つです。
- 1日に行う毛づくろいの回数・時間
- 脱毛班の有無
- 皮膚の異常
- 体の動きの異常
- トイレでの排泄時の異常
- 食欲
毛づくろいの回数や時間が普段より多い・長いと感じたら、痒みや違和感を感じている場合があります。
脱毛していなくても、ある部分だけ毛が薄くなってる場合は、皮膚が赤くなっていないか・湿疹やフケが発生していないかなどを確認してください。
いつも元気なのに走り回ったりジャンプしたりしないのは、関節痛かもしれません。
トイレでの排泄時におしっこがでなかったり血が混じっていたりする場合は、内蔵疾患の可能性があり、膀胱に炎症を起こしたと考えられます。
食欲低下についても同様に内蔵疾患の可能性があり、腫瘍の場合もなり危険です。
今回ご紹介した項目以外でも、普段と違うしぐさや行動をした場合、動物病院を受診しましょう。
猫の毛を引っ張る/撫でることで抜けにくくする対処法3つ

猫の毛を引っ張る/撫でることで抜けにくくするための対処法は、以下の3つです。
- 痒そうにしていたらすぐに動物病院を受診する
- 毎日ブラッシングをする
- 毛・皮膚の状態をチェックする
3つの対処法について、解説します。
痒そうにしていたらすぐに動物病院を受診する
早期発見・早期治療は、症状がひどくなる前に対応すれば回復も早くなるため、一番効果的な対処方法です。
過剰な毛づくろいや皮膚を噛んで出血や脱毛になる前に、早い段階で受診すると、思いがけない病気を発見することがあります。
飼い主さんがブラッシングしても毛づくろいをやめない場合は、すぐに動物病院を受診することをおすすめします。

動物病院を受診する際は、異常行動(過剰な毛づくろいなど)の動画を撮っておくと、獣医も判断がしやすいとのことでした。
猫のしぐさや行動に異変を感じたら、動画撮影の習慣をつけるといいですよ。
ちなみに、以下の内容は受診時に聞かれることが多いため、事前に答えられるようにしておきましょう。
- 異変はいつごろからみられるのか
- 症状はどんなものがあるのか
- 最近、生活する上でなにか変わったことがなかったか
毎日ブラッシングをする
「長毛種の場合は毎日、短毛種は週に2~3回ブラッシングを行いましょう」とネット上での書き込みを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、個人的には短毛種でも毎日のブラッシングをおすすめしています。
理由は、短毛種でも結構抜け毛があるからです。
我が家の猫たちも短毛種なのですが、毎日ブラッシングしないと大変なことになります!
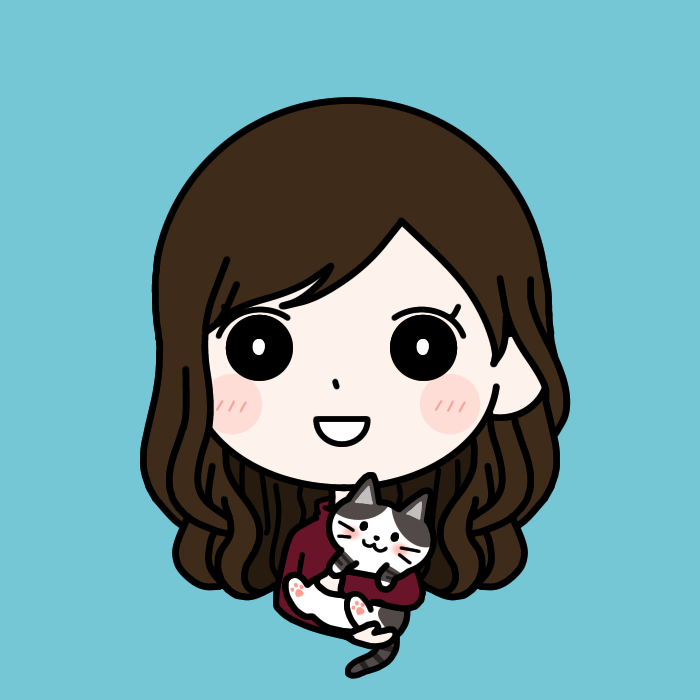
床だけでなく、ベッドやソファまで、毛だらけです。
抜け毛をそのまま猫の体につけたままにすると、毛づくろいをしたときに舐めとってしまって、毛球症になったり体に毛玉ができたりします。
毎日ブラッシングを行って、未然に防ぎましょう。
毛・皮膚の状態をチェックする
猫の毛の、特に生え際や皮膚の状態をチェックする習慣をつけましょう。
毛にフケや白い卵のようなものがついていたら、寄生虫の可能性が高いです。
また、皮膚の状態が悪いと赤くなっていたり、湿疹やかさぶたができていたりすることがあります。
毛と皮膚を清潔な状態に保つことや、栄養のある食事を与えるなど、健康に気遣うことは大切です。
毛の生え際や皮膚を触ると嫌がる猫は、なにか違和感を感じているのかもしれません。
判断に迷ったときは、獣医に相談しましょう。
まとめ:猫の毛を引っ張ると抜ける…実は表面についた抜け毛を取ってただけだった!

猫の毛を引っ張ると抜ける原因について解説しました。
考えられる原因はいくつかありますが、実際に毛が抜けたときの確認ポイントをチェックしてみましょう。
原因の中には、病気が炎症を発症している可能性もあるため、注意が必要です。
また、普段から抜ける毛を減らすための予防対策も、大切な健康管理と言えます。
今回ご紹介した内容に1つでも当てはまる項目があれば、早めに対応していきましょう。
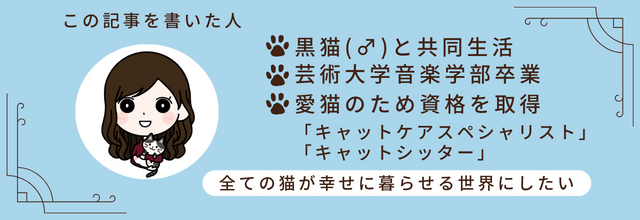

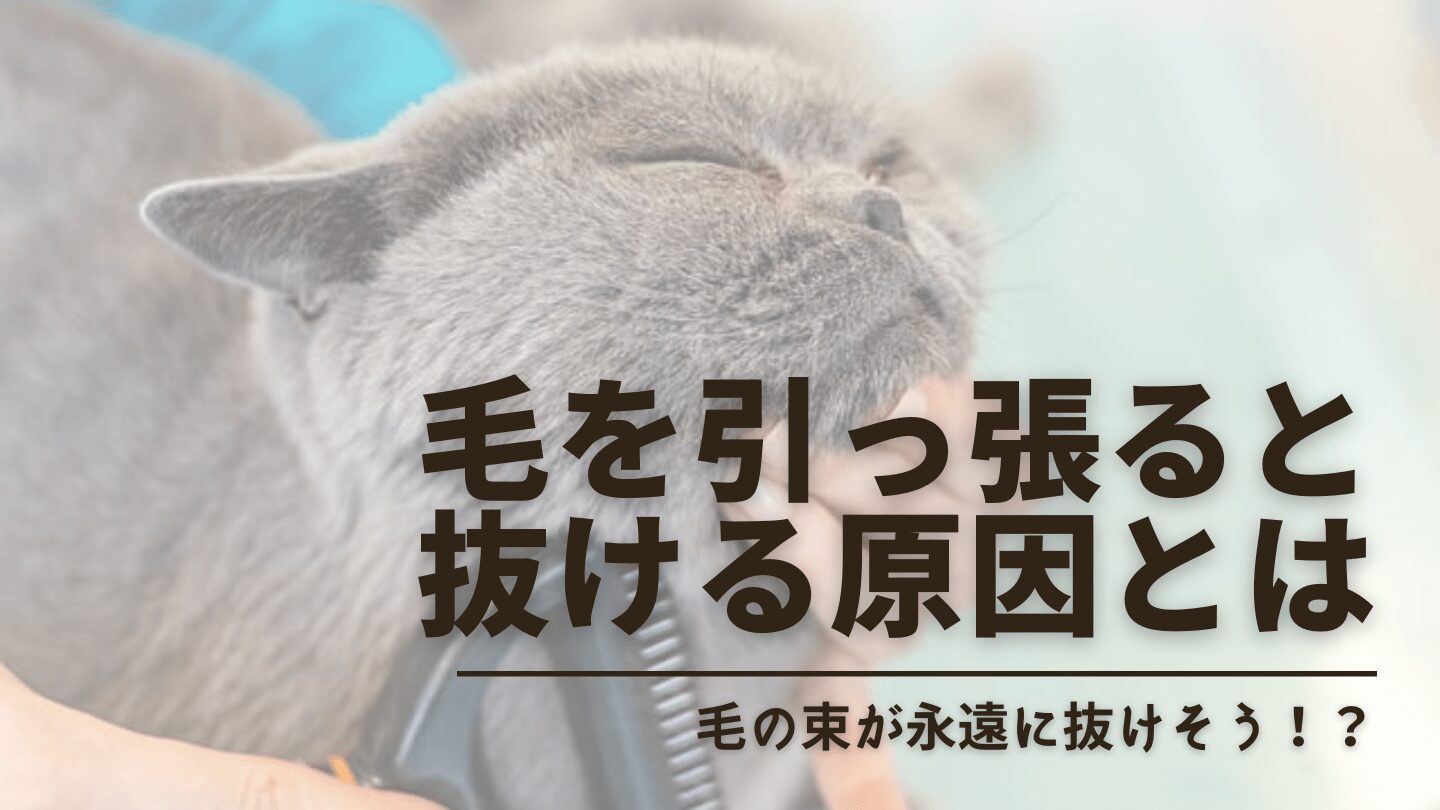
コメント